完全食はフードロス解消の手段となるか?

世界では、紛争や貧困による飢餓の問題はまだまだ深刻な状況です。その一方で生産された食糧を消費しきれず廃棄せざるを得ない「フードロス」が問題視されています。国連においては、2010年に SDGs(持続可能な開発目標)のなかで食品廃棄物の半減という目標が採択されました。完全食にはフードロスを抑止できる可能性があるのか見てみましょう。
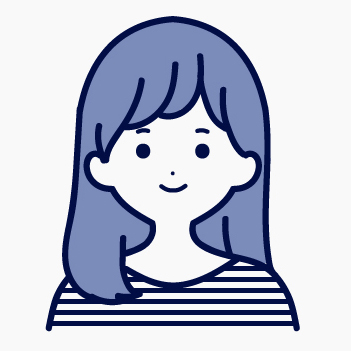
今回は、少し耳の痛い話になるかもしれません。テーマは「フードロス」です。
フードロスとは何か

まず、「フードロス」という言葉についておさらいしましょう。聞いた事はあっても、似たようなイメージを持つ食品廃棄と混同されている方も多いかもしれません。
食品廃棄とは、一般的に食べられないとされている部分(魚や肉の骨、卵の殻、果物の皮や種など)を捨てる事を指します。
一方フードロスは、上記以外の、まだ食べられる部分(果実の部分など)を捨てる事を指します。近年、このフードロスが抱える問題点が浮き彫りとなっています。
日本におけるフードロス
日本のフードロスはおよそ646万トン(2015年度推計)もあります。この量は世界で行われている食料援助量、およそ320万トンを2倍も上回ります。
日本人は毎年750万人の食事を1年間まかなえるほどのフードロスを出し続けていて、これは中国、アメリカに次いで世界で3番目です。

これは知らなかった。素直にビックリだね。
世界では飢餓によって命を落とす人がいる一方で、日本では食料が余り大量に廃棄されているのです。これには一般家庭で捨てられた食料だけでなく、その生産過程で廃棄された食材も含まれています。
フードロスは消費者側の問題?

日本におけるフードロスの半分は、家庭から出ています。家庭から出される生ゴミの中には、手つかずの食品が2割もあり、そのうちの1/4は賞味期限前にも関わらず捨てられているのです。
また、野菜の皮や肉の脂身など、工夫次第で十分に食べられる部位が過剰に捨てられているのです。安価であることなどを理由に買いすぎてしまったり、使い切れなかったりということもひとつの理由としてあげられます。

確かにセールで安く買ってしまって使わないまま賞味期限切れになってしまうこともあるよね…。

まあ、あるよね。正直。
高品質な食品を求めるあまり、形が悪い規格外品の野菜などは捨てられてしまうのも食品が大量に廃棄されている要因となっています。4人家族の1世帯では実に毎年約6万円分ほどの食料を廃棄していると言われています。
フードロスが起こす経済的なダメージが流転する
家庭からだけではなく、コンビニや飲食店、スーパーなど食品業界から出るフードロスも問題となっています。「インスタ映え」用の料理や商品を大量に頼んでも食べきれずに残してしまうことや、You tuberの「レストランの全商品頼んでみた」企画での食べ残しなどが問題視されたこともありました。

タピオカのブームの時に話題になってたな。ごく一部がクローズアップされたっていう側面もあるんだろうけど。
また、食品が流通するプロセスにも問題があり、「1/3ルール」(小売店が賞味期限の期間の1/3を過ぎた食品の納品を拒否できるという慣例)という商習慣があるため、納品期限・販売期限の切れてしまった食品は店頭に並ぶことはありません。
食品製造や流通に使用された資源やエネルギーは無駄となり、フードロスの発生が企業の利益率を著しく低下させます。その結果、小売価格を引き上げます。なぜなら、廃棄のための費用が販売価格に転嫁されてしまうからです。
大量に産出されてしまったフードロスは、全て事業系一般廃棄物となり、ごみ処理施設での処理に回されます。フードロスが増えれば増えるほど、運搬や焼却用の化石燃料が増え、焼却炉の維持管理費も増えて経済的負担が生まれてしまいます。

当然、廃棄するのにも手間や費用がかかるからだなー…。
さらに焼却する量が多いほどCO₂を排出するので、私たちは知らず知らずのうちに温暖化に寄与しているのです。ちなみに、消費者庁の参考資料によると、日本全体で1日に出る食品廃棄量はトラック1770台分、日本の年間の食品廃棄処理費用は2兆円に上るそうです。数字で見るとどれだけ深刻な問題なのかがわかります。

うーん…。
フードテックが変える未来

フードテックとはフード(食べ物)とテック(ICT技術)を組み合わせてできた用語です。近頃、フィンテック、エドテックといった「何か」と「テクノロジー」を組み合わせた言葉を耳にする事が多いかと思いますが、その中でもフードテックは特に注目を浴びています。フードテックというとビヨンドミート(人工肉)や、日本では回転寿司大手の「スシロー」が導入した総合管理システムも注目を集めていますが、完全食もフードテックに分類されます。様々なフードテックがフードロス問題はもちろん、これまでの食の在り方を一変させる可能性があり期待されています。
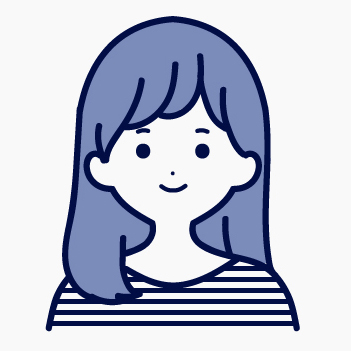
一概にフードテックと一言で言っても多くのテクノロジーがあります。気になる人はこちらを読んでみてください。
完全食がフードロスに与えるインパクト
完全食は「食のIT革命」と呼ばれています。なぜそう呼ばれているのでしょうか。完全食の特徴の1つに保存しやすいというポイントがあります。
野菜や肉、魚などの生鮮食品は毎日摂取したい食品であるにもかかわらず、あまり日持ちするものではありません。その点完全食は賞味期限が長い商品が多いです。
例えばベースフード社の製品であるベースパスタとベースブレッドは常温保存でも共に賞味期限は1ヵ月ほどあります。生麺と焼かれているパンであるにもかかわらず、これだけの保存性の良さを実現しているのです。
通常、消費する立場ではここまで考えることは無いかもしれませんが、この企業努力は偉大です。完全食ではない他社の角食パンなどの賞味期限はせいぜい1週間程度でしょう。その他の現在販売されている完全食もほとんど長期保存が可能となっています。

栄養を抽出して再構成するテクノロジーが注目されがちだけど、長期保存も1つのテクノロジーなんだね。
COMP社の主力製品であるグミだと5ヵ月。パウダーだと1年。発売初日で完売するほど人気がある日清食品の「All-in-PASTA(オールインパスタ)」は生麺ではないですが8ヵ月といった驚くほどの長期保存が可能となっています。
さらに完全食にはコストパフォーマンスが高いというメリットもあります。普通のパスタやパン、米といった主食と比べてしまうとどうしても高くなってしまうのですが、配合されている栄養ベースで考えると、実は物凄くコスパが高いのです。
1日に必要な栄養を考えて野菜や魚を買っているととても完全食のコスパには歯が立ちません。まだまだ日本での完全食のイメージはダイエット食品みたいな置き換え食品に捉えられてしまいがちですが、完全食は理想的な栄養バランスな上にコスパが良くて、長期保存が可能な新しい概念の万能食品なのです。
普段の食事を完全食に置き換える人が増えることによって、賞味期限が起因での廃棄は当然少なくなりますし、日持ちするので買いすぎても消費に困ることは少ないでしょう。その為フードロスの深刻さを和らげるとても容易な手段となるのです。

テクノロジーは偉大だね。
完全食が普及すれば世界はどう変わる?

地球規模で考えた場合、食料問題にも大きな影響があるでしょう。現在地球の人口は増加し続けており、2005年には65億人だった世界人口は現在2020年では77億人を超えています。
2055年には100憶人を突破するという予測もあります。貧困率は徐々に良くなってはいるものの、未だに政治や紛争問題から飢餓から逃れられない人達が8億人以上います。今後も増加する人口によって供給量においては深刻な食料問題を抱えています。
ところがその一方でフードロスの問題があり、抜本的な解決手段を必要としています。「フードロス大国の日本」において現在より完全食が普及すれば、必然的に食品を輸入に頼る量が減るので、それまで日本に輸出していた食料が必要な人の手に渡るようになるかもしれません。
完全食が普及する事によって大量生産が可能になりますから、コストを抑えて作ることができるようになります。そうなると販売価格も下がり更なる普及が見込めるので、間接的ではありますが、フードロスを抑えることが飢餓を救うことになるのです。
もちろん日本だけではなく、フードロス問題は世界中で深刻な問題として捉えられています。完全食の開発はこうした食料問題や環境問題の観点からも、非常に注目されています。
まとめ

日本では豊かな生活を送っている人が多いですが、世界では貧困に苦しみ明日の食べ物さえ自分で確保できない人々も多くいます。そのことを常に頭の片隅に入れておいて食品の廃棄を減らすように、1人1人がもっと責任をもってこの問題に取り組まなければなりません。そのための手段として完全食を取り入れることはとても個人にとって意義のあるものになるでしょう。
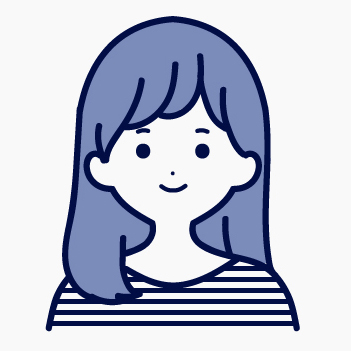
今回はフードロスについての問題を取り上げました。完全食のように新しい食のテクノロジーによって解決する手段を見出したいものです。
-
前の記事

ビーガンって何だっけ?ベジタリアンとの根本的な違い。 2020.03.26
-
次の記事

コンビニで完全食が販売されるまで 2020.10.19
